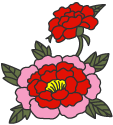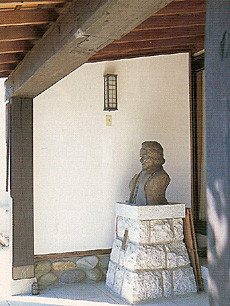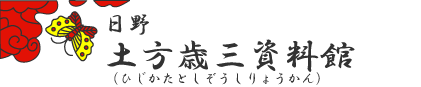
| 〒191-0021 東京都日野市石田2丁目1−3 開館日:第一・第三日曜日の12:00〜16:00 (祝日・連休などは開館してくれている日があるので公式HPをチェックされた方がいいでしょう。) 入館料:500円(2006/05現在)・資料館裏手に専用駐車場が4台分あり。 |
|||||||||||||||
 |
土方歳三の生家…とされているが、実際はちょっと違う。 もともと土方家は石田寺裏手の多摩川沿いの一角にあった。 歳三が12歳の頃(1846年)に多摩川洪水で被害を受けて現在の土方家の場所に母屋等を移転した。 現在では母屋も建て直され、その際に土方家子孫の方々が家の一部を資料館として改装して一般開放している。 資料館の入り口に母屋の大黒柱や長者柱を使用するなどして昔の形を残すように工夫されている。 子孫の方がマイクをとって遺品の説明やそれにまつわるエピソードなどを話してくれるが、その内容がどんな資料にも載っていないような素晴らしいものばかり。 資料館内は撮影禁止だが歳三の愛刀・和泉守兼定や鉢金、石田散薬の薬箱、豊玉宗匠の句集などを見学することができる。 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
巡った日:2006/05/04 |
|||||||||||||||